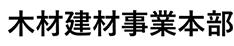2025.10.31
非住宅建築の大空間、木造化の壁をどう乗り越える?(その2)
― 阿蘇くまもと空港 木造トラス屋根をめぐる二つの闘いの物語(開発編) ―

設計監理:株式会社日建設計
工事監理:株式会社梓設計
施 工:大成建設株式会社
木構造屋根組工事:三井ホーム株式会社
こんにちは。S造・RC造からの非住宅建築の木造化をワンストップで支援する木構造ファブリケーター、木構造営業部のHです。
前回に引き続き、「非住宅建築の大空間、木造化の壁をどう乗り越える?」の第2弾として、今回はコネックトラス採用事例である阿蘇くまもと空港ターミナルビルを深掘りしていきます。
前回に引き続き、「非住宅建築の大空間、木造化の壁をどう乗り越える?」の第2弾として、今回はコネックトラス採用事例である阿蘇くまもと空港ターミナルビルを深掘りしていきます。
2016年4月の熊本地震により旧ビルが被災した阿蘇くまもと空港は、復興のシンボルとして、2023年3月に国内線・国際線一本型の新ターミナルビルへと生まれ変わりました。
このプロジェクトの裏側にあった挑戦と成功の物語、当社の知られざるストーリーをご紹介します。
このプロジェクトの裏側にあった挑戦と成功の物語、当社の知られざるストーリーをご紹介します。
熊本の木材を使った大屋根
このプロジェクトには、震災復興の象徴として「天井に美しい木架構を目指す」というデザイン面の理想とともに、「地元・熊本の木材を使う」という大きな使命が課せられていました。
しかし、その条件は厳しく、「高価な集成材などの特殊寸法部材は使わず、一般に流通する小国杉のツーバイフォー材(2×4材)を使い、10mの大スパン空間を成立させること」でした。
しかし、その条件は厳しく、「高価な集成材などの特殊寸法部材は使わず、一般に流通する小国杉のツーバイフォー材(2×4材)を使い、10mの大スパン空間を成立させること」でした。
開発担当のOは、2×4材をメタルプレートコネクター(コネック)で接合したワーレントラス構造に着目し、構造解析上は設計が可能だと確信していました。
しかし、相手は国内最大規模の木造屋根架構です。解析データだけでは、ゼネコンや設計事務所の「本当に大丈夫なのか?」という、未知の構造に対する当然の不安を払拭することは容易なことではありませんでした。
しかし、相手は国内最大規模の木造屋根架構です。解析データだけでは、ゼネコンや設計事務所の「本当に大丈夫なのか?」という、未知の構造に対する当然の不安を払拭することは容易なことではありませんでした。
そこでOが選んだのは、解析技術だけでなく、地道かつ実直な「実物による証明」でした。
まず、意匠(風合いやライティング)の確認、そして最も重要な鉄骨(S造)と木造トラスの接点となる「納まり」を検証するため、実大模型(モックアップ)を製作。さらに、現場の暴露状態での効果を確かめるため、防水メーカーと共同で防水施工用のモックアップまで作り、技術的な裏付けを一つ一つ着実に積み上げていきました。
まず、意匠(風合いやライティング)の確認、そして最も重要な鉄骨(S造)と木造トラスの接点となる「納まり」を検証するため、実大模型(モックアップ)を製作。さらに、現場の暴露状態での効果を確かめるため、防水メーカーと共同で防水施工用のモックアップまで作り、技術的な裏付けを一つ一つ着実に積み上げていきました。
そして決定打となったのは、設計仕様である10mスパントラスの実大構造試験です。
大分大学の田中准教授監修のもと、多くの関係者を招いて公開試験として実施。関係者が見守る中、トラスが設計耐力を十分に満足する強度を持つことを、実験により検証したのです。
Oは、大規模な木造建築を現実にしてもらうためには「自分の目で見て、納得してもらう」ことが何よりも重要だと痛感しました。
この粘り強い技術証明が、不特定多数の目に触れる復興のシンボルへの道を確かなものとして切り開いたのです。
大分大学の田中准教授監修のもと、多くの関係者を招いて公開試験として実施。関係者が見守る中、トラスが設計耐力を十分に満足する強度を持つことを、実験により検証したのです。
Oは、大規模な木造建築を現実にしてもらうためには「自分の目で見て、納得してもらう」ことが何よりも重要だと痛感しました。
この粘り強い技術証明が、不特定多数の目に触れる復興のシンボルへの道を確かなものとして切り開いたのです。

設計監理:株式会社日建設計
工事監理:株式会社梓設計
施 工:大成建設株式会社
木構造屋根組工事:三井ホーム株式会社
※写真提供:熊本国際空港株式会社
次回、「非住宅建築の大空間、木造化の壁をどう乗り越える?(その3)」では、この巨大屋根を実際に組み上げた現場担当Yの奮闘を描く「現場編」をお届けします。
お楽しみに!
お楽しみに!